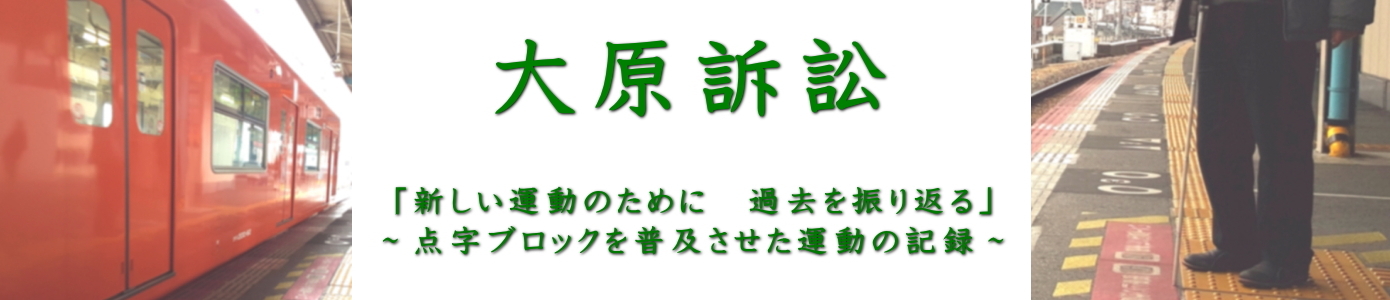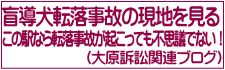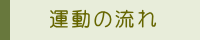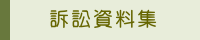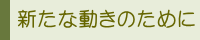幻の訴状(案)と弁護団から消えた弁護士
大阪地方裁判所に訴状を提出したのは昭和51年7月であった。
大原さんから依頼を受けて、約1年間を調査に費やし、やっと訴状作成の段階になった。
訴状の作成は、1年後輩の若手弁護士に依頼した。
出来上がった訴状(案)を見たが、これでは使えないと思った。
訴状は、こちらがどういう法律的な根拠で損害賠償を国鉄に請求しているかを明らかにするものであり、訴訟の方向を決定するものだ。
又、最初に裁判所の目に触れる書面であるため、「なるほど」とうならせるような説得力のある内容にしなければならない。
だが、出来上がった訴状はそのようなレベルに達していなかった(と思った)。
もちろん、人にはそれぞれの文章の書き方があり、そこに個性が出るのだが、訴状からおのずから伝わってくる迫力があるはずだが、それがなかった。
一部を書き直すことだけではなく、その案は全面的な改定が必要だと思ったので、一から書き直した。
その結果、元の起案は影も形もなくなった。
この全面改定は、予期していなかった結果を招いた。
訴状案をボツにされた弁護士が、弁護団から脱落したのである。
自分の心血を注いだ(はずの)《訴状という作品》が全否定されたのだから、彼としては自分を全否定されたという気持ちになったのだろう。
元の起案をできるだけ活かせるように修正を加えればよかったのかもしれない。
ただ、まだ若かった私はそんな配慮をすることができなかった。
「これではだめだ」と切り捨てて、一から自分で作り始めたのだから、彼としては立つ瀬がなかっただろうし、一方的なやり方に面子もつぶれ、怒りも感じただろう。
弁護士から最高裁判事になった方の話を聞いたことがある。
その人は、若い弁護士の起案を訂正するときに、できるだけ元の文章を活かして直しておられたという。
一から書き直した方が早いと思われるときでも、丁寧に書き直しておられたそうである。
あの時の私に、そのような優しさがあればよかったのに、とも思う。
しかし、当時の私にはそのような優しさはなく、独走、独断で変更をした。
大原訴訟のような、その時点では未来を切り開くような訴訟は、ある面、独断的であるからこそできた訴訟でもあった。
誰か、先頭に立って引っ張ることで進む訴訟でもある。
そういえば、この大原訴訟のホームページも、他の弁護士に相談することなく、独走、独断で作っている。
弁護士生活40年を経過した現在でも、独走、独断変わっていないというべきだろうか。
(弁護士 大澤龍司)