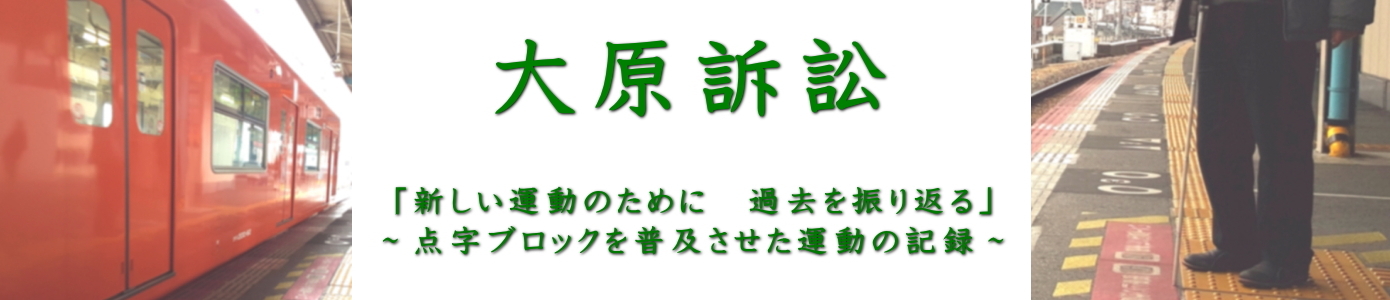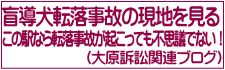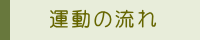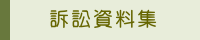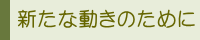※左が上埜さん、右が武田さんです。
障害者の傍聴権の獲得(手話通訳の巻)
傍聴席最前列に立っての手話通訳の実施
大原訴訟はもちろん裁判であり、第一審、第二審、最高裁でそれぞれ判決がなされた。
ただ、判決に至るまでに毎回、法廷で弁論手続きや証拠調べが行われる。
これらの手続きは公開の法廷で行われた。
大阪地裁の2階にある大法廷(座席数は約100弱)で行われたが、もちろん、傍聴が可能であり、裁判の経過を見ることができた。
大原訴訟を提訴する前に弁護士と「大原訴訟支援の会」で決めたことがある。
《この訴訟は決して、判決だけの訴訟にはしまい》と。
この裁判の手続きの中で、障害者の権利を実現していこうということも私達の獲得目標であった。
具体的に言えば、まず、手話通訳の問題があった。
聴覚障害者も当然、裁判の傍聴が可能である。
しかし、大原訴訟のような障害者の権利に関する事件であれば、当然、聴覚障害者も傍聴を希望するだろう。
現に支援する会には倉田さんという聴覚障害者も参加しており、傍聴にも来られていた。
通常は、横の座席に座った人が聴覚障害者に手話通訳することが多い。
しかし、複数の聴覚障害者が来る場合、手話通訳の数が多数必要になり、到底、対応できない。
そのため、すべての傍聴人に見えるような形で手話通訳を行いたいと裁判所に申し入れた。
裁判所の回答はそれでも良いということであった。
そのため、大原訴訟では、傍聴席側から見て、最前列の左端に立っての手話通訳が実施された。
なお、手話通訳は支援する会の武田さんと上埜さんの2人に担当してもらったという記憶がある。
あるとき、どちらかから《今日は聴覚障害者が来ないんですが、どうします?》という話があった。
《いつもどおり、手話通訳はする!》と答えた。
聴覚障害者が来た場合、その人たちに裁判の内容をわかってもらうようにする。
それは裁判を公開する裁判所の義務であり、裁判の当事者である視覚障害者にとっての、又、傍聴に来た聴覚障害者にとっての「権利」でもある。
獲得した「権利」は使わなければならない。
法廷で手話通訳がいつも行われている、それが日常の風景として定着するまで、たとえ、聴覚障害者が来なくともやり続けること、それが「権利」をより確実に固めることである。
また、そんな実例を営々と積み重ねることが、将来、また、提起される訴訟の傍聴にくるであろう聴覚障害者の「権利」確保につながるであろう。
結局、毎回、手話通訳は実施され、これは第1審の大阪地裁でも、その後の控訴審の大阪高裁でもなんら問題なく実施された。
ただ、判決に至るまでに毎回、法廷で弁論手続きや証拠調べが行われる。
これらの手続きは公開の法廷で行われた。
大阪地裁の2階にある大法廷(座席数は約100弱)で行われたが、もちろん、傍聴が可能であり、裁判の経過を見ることができた。
大原訴訟を提訴する前に弁護士と「大原訴訟支援の会」で決めたことがある。
《この訴訟は決して、判決だけの訴訟にはしまい》と。
この裁判の手続きの中で、障害者の権利を実現していこうということも私達の獲得目標であった。
具体的に言えば、まず、手話通訳の問題があった。
聴覚障害者も当然、裁判の傍聴が可能である。
しかし、大原訴訟のような障害者の権利に関する事件であれば、当然、聴覚障害者も傍聴を希望するだろう。
現に支援する会には倉田さんという聴覚障害者も参加しており、傍聴にも来られていた。
通常は、横の座席に座った人が聴覚障害者に手話通訳することが多い。
しかし、複数の聴覚障害者が来る場合、手話通訳の数が多数必要になり、到底、対応できない。
そのため、すべての傍聴人に見えるような形で手話通訳を行いたいと裁判所に申し入れた。
裁判所の回答はそれでも良いということであった。
そのため、大原訴訟では、傍聴席側から見て、最前列の左端に立っての手話通訳が実施された。
なお、手話通訳は支援する会の武田さんと上埜さんの2人に担当してもらったという記憶がある。
あるとき、どちらかから《今日は聴覚障害者が来ないんですが、どうします?》という話があった。
《いつもどおり、手話通訳はする!》と答えた。
聴覚障害者が来た場合、その人たちに裁判の内容をわかってもらうようにする。
それは裁判を公開する裁判所の義務であり、裁判の当事者である視覚障害者にとっての、又、傍聴に来た聴覚障害者にとっての「権利」でもある。
獲得した「権利」は使わなければならない。
法廷で手話通訳がいつも行われている、それが日常の風景として定着するまで、たとえ、聴覚障害者が来なくともやり続けること、それが「権利」をより確実に固めることである。
また、そんな実例を営々と積み重ねることが、将来、また、提起される訴訟の傍聴にくるであろう聴覚障害者の「権利」確保につながるであろう。
結局、毎回、手話通訳は実施され、これは第1審の大阪地裁でも、その後の控訴審の大阪高裁でもなんら問題なく実施された。
(弁護士 大澤龍司)